
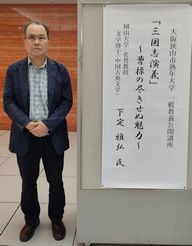
岡山大學名誉教授
下定 雅弘 氏
第2回
一般教養科目公開講座
於:SAYAKA大ホール
2025年6月19日
【三国志演義-曹操の尽きせぬ魅力-】

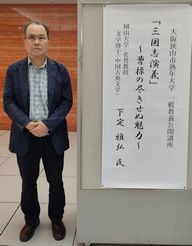
岡山大學名誉教授
下定 雅弘 氏
![]()
| 講演要旨 「三国志演義」曹操は、この小説の主人公の一人。「三国志演義」の淵源は元末明初の羅貫中作(現存せず)、今日普通に読まれているには、 清初の毛倫(もうりん)毛宋崗(もうそうこう)改訂「三国演義」全120回毛宋崗「読三国志法」は、 「智」絶の諸葛亮・「議」絶の関羽・「奸」の曹操を三絶とす。曹操は、中国でも日本でも、悪役の印象が強い。だが曹操は「三国志演義」においても、悪漢でありつつ、同時に人間味溢れる、尽きせぬ魅力に満ちたキャラクター。 |
||||
| 一 はじめに曹操の一生をお話しする。
(1)29歳 曹操は宦官の養子の子供である。後漢末の黄巾の乱の鎮圧のとき董卓の討伐に加わり頭角を現す。 黄巾の乱で鎮圧した兵士を自分の部下にした。 (2)37歳 袁紹と協力して董卓を殺そうとした。袁紹が河北を押さえる。 袁紹が敵。 (3)45歳 袁紹を官渡の戦いで破る。 中国の北半分を曹操がおさえる。曹操が後漢の丞相(天子を助けて国務をとった大臣)になる。 (4)54歳 呉の孫権・蜀の劉備が協力して赤壁で曹操を破る。魏・呉・蜀の天下三分の形勢が定まる。 (5)64歳 曹操皇帝に次ぐ地位の魏王になる。 (6)曹操の死(66歳)は後晋の司馬懿が権力を握る。 (7)曹操 人材登用は才能重視、屯田を行う。 詩文・音楽にすぐれ、文学もトップ 兵法にすぐれ、孫氏の兵法の注釈を施した。 二 三国志演義の説明 1悪人曹操 (1)四回 とにかく人を殺した。 董卓(後漢の皇帝献帝を擁立して専横を振るい、部下の呂布に殺され た。)と対立して殺すことに失敗。陳宮(ちんきゅう)と共に逃げていく。 (2)十回 徐州で太守(中国古代の郡の長官)に父親を殺された報復に徐州の領民を殺しつくし、墓をすべて掘り返した。(3)四十八回 赤壁の戦いのまえに船上で酒宴をしていたときに、曹操が詩文「短歌行」を詠んだとき部下に不吉と言われて部下を殺してしまった。翌日酔いが覚めて限りなく後悔し、部下の子供に手厚く葬るがよいと言って柩を護衛する兵士を与えて帰郷させた。(4)六十八回 曹操が魏王になることを反対した尚署(臣下から皇帝に対して上奏を取り扱う役職)を撲殺2「善人」曹操 (1)十六回 呂布を討伐しようとする戦いのなか、曹操が襲われたとき、曹操の部下のてんいが敵を蹴散らして守るが落命する。曹操部下のてんいのために葬儀を行い大声で泣いて 供物を捧げた。(2)六十七回 曹操が道教の集団の五斗米道(ごとべいどう)を降参させて漢中地方を平定したとき劉備の蜀を攻撃するよう進言した司馬懿に「兵士たちは遠征で苦労してきた。 しばらく休ましてやらねば」と軍をうごかさなかった。(3) 七十八回 曹操が臨終のとき侍女たちに貯えてあった名香をわけあたえて心遣いを示した。享年66歳 (4)十六回 劉備が曹操を頼ってやってきたとき、部下じゅんいくが「劉備は英 雄です。 いま殺しておかねば、後のわざわいになります」といったが、別の 部下の郭嘉(かくか)は「いま殺せば、天下の智謀の士,ご前に馳せ参じるのに二の足 を踏むことになる」と進言した。曹操は劉備を受け入れた。(5)二十五回~二十七回 曹操46歳 関羽、曹操の部下が降参を勧めるのに対し三つの条件をつける。 曹操それを承諾して関羽を丁重にもてなす。関羽に陣羽織・名馬を与えて懇切の限りを尽くした。 関羽もこれにこたえて、袁紹の戦いで袁紹の猛将を討ち取るとこれを置き土産に「劉備の所在がわかれば曹操のもとを辞す」という条件で劉備のもとに立ち去っていった。 曹操は関羽のことを思って嘆息してやまなかった。 (6)三十一回 曹操が官渡の戦いで大勝を収めたとき、この機に袁紹を攻めるように進言した部下に「今は作物が熟する時百姓に迷惑かけるのはよくない。秋の収穫が済んでから攻めても遅くはない」と言った。 三 「英雄」曹操 (1)一回 46歳 よく人物みることで知られている汝南は曹操のことを「あなたは治世の能臣、乱世の姦雄だ」と言って、曹操はこれを聞いて大いに喜んだ。 (2)十八回 44歳 曹操の部下の郭嘉は道・義・治・度(量)・謀・徳・仁・明・文・武の全てにおいて曹操が袁紹に勝るといった曹操に対する至高の絶賛である。以上  |
![]()
2025年6月 講演の舞台活花

活花は季節に合わせて舞台を飾っています。
平成24年3月までの「講演舞台活花写真画廊」のブログはこちらからご覧ください。
講演舞台写真画廊展へ
![]()