
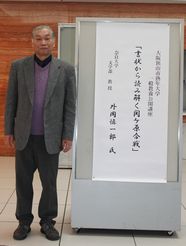
奈良大学文学部教授
外岡 慎一郎 氏
第8回
一般教養科目公開講座
於:SAYAKA大ホール
2025年1月16日
【書状から読み解く関ヶ原合戦】

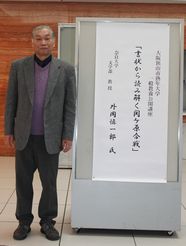
奈良大学文学部教授
外岡 慎一郎 氏
![]()
| 講演要旨 関ケ原合戦はほぼ半日で終結した合戦です。しかし、戦いの前にはたくさんの書状が取り交わされ、そこに載せられた言葉に一喜一憂する武将たちの姿がありました。今回はそうした場面のいくつかを紹介します。 |
||||
| はじめに
今日のテーマは皆さんがよくご存じの関ケ原の合戦です。合戦と言えば最近テレビで「最強の武将」「最強の城」などのタイトルがよく話題に上がっています。「最強の武将」などのアンケートに答えたこともありますが、私の観点では死なずに最後に生き残った武将が最強ということになります。 家康や秀吉は最強の武将と言われていますが、戦場に出て自分で刀を抜いて戦ったのかと考えると、まずそんなことはなかっただろう。 信長は矢面に立って戦っていますが、秀吉や家康は自分が直接戦う場面はほぼなく、それでもどうやって戦わずして勝つかということを考えて行動して、その結果として合戦で負けなかった。 つまり「負けない武将」が「最強の武将」となりますから、多くの武将にとって勝ち馬に乗ってでも生き残ることが条件になります。 実際の戦場で戦う勇将は100人を倒し、知将は10000人を倒すと言われますが、実際に一人の勇将がどれくらいの敵を倒せるかというと、槍や刀を使いすづければ疲れも出てとても100人とはなりません。バッタバッタと倒す時代劇のようにはなりません。 実物の刀を持った経験のある方は分かると思いますが、それを振り回してその勢いで相手の急所を突いて失命させるというのは簡単なことではありません。
次に「最強の城」ですが、どんなに強固に構築された城でも落ちない城はない。内応者をつくるなど、色々な手法を駆使して最終的には落とされる。 一方、堅固に構築された城が要塞として実戦で使用されることなく、現代の発掘調査まで埋もれているものが多々あります 合戦になった関ケ原の周りにはいろいろな城がありましたが、関ケ原合戦の場合は陣城としての機能にとどまり、城をめぐる攻防戦はありませんでした。 さて、関が原に終結した15万ともいわれる軍勢は、石田方と徳川方、殆ど互角の勢力だったが、何故半日ぐらいで終わってしまったのだろうか、という謎がよく話題になります。 それはおそらくこの合戦があらかじめセッティングされた合戦だったからだと考えるべきと思います このセッティングをどう読み解くかについて私が注目したのは合戦以前に取り交わされた書状です。これに関する拙著『関が原を読む』を読んでくれたNHKのディレクターが中心になって構成された特番がありました。ご覧いただいた方もここにおられるかもしれません。 この著作で紹介した書状は数十点ほどですが、実際に私が集めたのは数百点あります。この書状の全容を通しての話にしましょうとなり、半年ほどかけて話をしながら番組になりました。 今日の視点は徳川家康、石田三成と毛利輝元の3人について書状を通して動きを読んでみます。 結論を急ぐようですが、関が原で対峙した時、家康と三成は最後の場面で、この戦いは長引かせないほういいだろうと考えていたとおもいます。長引くとまた戦国時代に逆転してしまうと。 ところが、毛利輝元は両軍が西軍と東軍という形で長引くほうが自分にとって有利に交渉が実現できるのではないか考えていたと思います。そうしたことも含め、三成、家康、輝元それぞれの思惑と誤算に注目していきます。 そして、慶長5年9月15日に関が原で両者が対峙するまでに、それぞれが危機を迎え、そこでどのようにこれを克服しようとしたのか、またはできなかったために敗けたのかを考えることを目途としてこれからご紹介していきます。 1. 徳川家康 最初の誤算 徳川家康が豊臣正規軍を率いて6/16に会津 上杉景勝討伐に出陣するとこから話を始めます。 家康が「上杉討伐」を名目に豊臣正規軍を率いて出陣したときに発令されたのが(史料1)「豊臣奉行衆連署書状」です。 内容は各自が利害にもとづき勝手にバラバラに動くことがないように定めた軍律で、豊臣奉行衆が発した重みのあるものです。 一.七月十日以前の出陣禁止(この年の収穫=兵糧に関係する日程か) 一.現地司令官は家康であること 一.兵糧は豊臣方で準備したものと自己調達で賄い、現地調達は禁止 と指示しています。 この時点で家康は間違いなく豊臣正規軍の総司令官の立場にありました。 ところが、大坂で予想外の政変・クーデターがおこります。(史料2)豊臣奉行衆連署書状 7/17「内府ちがいの条々」をご覧ください。 この文書は13か条にわたって家康の非違を糾弾し豊臣政権から追放するものであり、家康は謀反人に転落したわけです。 たとえば、上杉討伐軍は、江戸にいる家康が、東北の一大勢力である上杉を屈服させるという私的な事情で豊臣政権の力を借りて勝手に出かけて行ったものに過ぎないと、このなかで言っています。 家康は豊臣秀吉が亡くなった後、秀頼の後見として豊臣政権を支える立場にありました。ところがその一方で、私的に大名と婚姻関係を結んで党派を作るなどもあり、三成はこれを非難したのですが、三成糾弾の集団訴訟があって結局三成は政権から脱落して佐和山城に蟄居させられてしまいます。慶長4年閏3月(関ケ原合戦の1年半前)のことです。 ですから三成が家康と対峙するには、 家康を謀反人にして、自分が豊臣正規軍のリーダーとして家康を討つという大義名分が必要だったのです。豊臣政権に強行復帰してクーデターという手段で大義名分を獲得したのです。 家康の第一の誤算はこのクーデターになります。家康がわざと大坂を留守にして三成の決起を促したとの陰謀論が語られることがありますが、これは当たらない。結果から導き出した俗説です。 さて、7/24に下野小山に集結した家康と上杉「討伐」軍は、クーデターは石田三成・大谷吉継の共謀と判断し、「討伐」中止と上方帰還を決定します。上杉討伐軍の評定の議題は上杉討伐ではなく、石田・大谷の討伐だったのです。 そして7/26ころから大名ごとに三々五々討伐軍の帰還が開始されます。 2.徳川家康二度目の誤算 小山から西に向かった上杉「討伐」軍は福島正則、黒田長政、藤堂高虎、池田照(輝)政、長岡長興ら豊臣秀吉恩顧の武将が中心で、これに徳川家康の直臣 井伊直政、本多忠勝が帯同することになります。 家康がクーデターを知るのは7/29頃で、三成が秀頼と奉行衆を擁して毛利輝元とともに豊臣政権を主宰してしまった以上、実力で派遣を得るほかなくなる わけです。ただ、家康としては豊臣の足かせが外れたことで、戦いやすくなったという側面もあります。 家康は確約を取るため書状を各武将宛に配り、先鋒衆は井伊直政の指図に従うよう指示し(史料3)、上杉討伐軍はそれぞれに西に向かい、おそらくは8/11までに福島正則の居城清州城に終結します。 ところが福島らは先鋒衆は清須からなかなか動きません。この辺りの事情は軍記類に依拠するしかないのですが、福島らは家康が江戸から動かないことに不満を募らせ、また家康も豊臣の息がかかった福島らが動かないことには安心して江戸を発てないとして焦る。家康二度目の誤算です。 結局家康は江戸から村越茂助を清須へ派遣し、口上で家康の真意を伝えて先鋒衆へ進軍を促すことになります(史料4)。 先鋒衆は8/22木曽川を渡り上方衆(西軍)を撃破し、8/23岐阜城を攻略し、石田三成、宇喜多秀家、島津義弘が終結・籠城していた大垣城の北西に位置する赤坂付近に8/25~8/26ころ陣取ります。 この先鋒衆の破竹の進撃で家康の先鋒衆への疑心暗鬼が解消し、これ以降上方衆(西軍)から次々と寝返りが出て、家康は勝算を得ます。 後世からみると家康は勝つべくして勝ったようにみえますが、二度の誤算に見舞われながらも、これにうまく対処した結果ともいえます。 3. 石田三成の誤算 クーデターに成功した三成は秀頼を中心にした、二大老(宇喜多秀家・毛利輝元)四奉行(石田三成・増田長盛・長束正家・前田玄以)の集団指導体制をしき、家康との戦いに向けた戦略として、当初は尾張・美濃国境で秀頼への忠節を問い、上杉「討伐」に参加した武将たちの帰還の可否を判断する計画を持っていたようです(史料5、最初の条)。 三成はまた真田~上杉との間でホットラインを形成しました。史料5の二条目にみえるように、石田方から真田昌幸に使者3人を送り、そのうちの2人に真田からの使者1人を加えて上杉に送り、上杉からの返事も真田経由で石田に返すよう指示しており、相互の情報共有を信頼の証としたことがわかります ところが大河ドラマ『真田丸』でも描かれましたが、真田家が二つに割れ、長男の信幸は家康方に付きます。これはホットラインの維持には大変な障害となります。史料6の三成書状には「六かしき儀」(困難なこと)は人を増やし、信頼できる人に書状を託す(「そくたく」=嘱託)など工夫(「御馳走」)してほしいとあります。 史料7は真田昌幸宛の石田三成書状ですが家康に味方した浅野家に残っています。つまりこの書状は途中で家康方に奪われた可能性があり、石田側の情報網が崩れたことを示しています。 その後の動きで見ると、先ほど紹介した先鋒衆が木曽川を渡り上方衆(西軍)を撃破し8/23岐阜城を攻略します。尾張・美濃の国境で秀頼への忠節を問い、上杉「討伐」に参加した武将たちの帰還の可否を判断する計画も、上杉・真田とのホットラインも頓挫し、石田三成が考えていた作戦が次々と崩れていきます。三成にとっては決定的な誤算でした。 4.毛利輝元の誤算 毛利輝元は家康が上杉「討伐」軍を率いて大坂を発った時はまだ広島にいましがが、石田らからの要請を受けて海路二日で大坂に到着しました。大坂城西の丸にいた家康の留守居を追い出し、豊臣秀頼、淀殿を補佐する立場になります。 その後の輝元の動きを見ると、家康に味方した四国の大名所領へ軍を侵入させ、文字通り西軍武将としての戦争を遂行しています。輝元に領土的野心があったことは疑えませんが、大義は西軍の戦いということになります。 史料8の毛利輝元書状(村上元吉ほか宛8/27)には、伊予の東軍方(藤堂高虎、加藤嘉明)城郭攻略についての指示とともに、毛利秀元・吉川広家らが伊勢(安濃津城)を攻略したこと、東軍の美濃侵入への対応が報じられています。 輝元の西への軍事行動については、振り返れば、文禄4年(1595)の徳川家康・毛利輝元・小早川隆景連署の起請文で秀頼擁護の秀吉への誓約をした折に、秀吉が「坂東」は家康、「坂西」は輝元・隆景に任せるとしたことを意識していたのかもしれなません。 ところが、史料9輝元家臣の益田元祥書状(榎本元吉/毛利輝元宛9/12)を見ると、益田元祥は関ケ原東方の南宮山付近にいたのですが、家康が到着するとの報を得たにもかかわらず、輝元からは何のしじもないことに疑義を述べています。大坂の輝元と南宮山の情報共有が不全に陥っていたようです。 さらに史料10毛利輝元書状(益田元祥宛9/13)は史料9への返書として読めますが、福原広俊を使者として送り、万事安国寺恵瓊の裁量に任せると述べていて事実上家康との戦いの前線指揮から離脱したようにもみえます。 輝元は大坂以西を自分に任せるよう、家康と交渉することを考えていた可能性もありますが、実に甘すぎる展望であったことは後にわかります。皆様ご存知のように、輝元は領国すべてを失いかねない危機に瀕し、吉川広家の懇願によってようやく周防・長門(山口県に相当)を確保するのです。 輝元にとっては東軍先鋒衆の素早い進軍で西国計略が完遂できなかったことが何よりの誤算、さらには大きく領国を失うことになったのも甘い見通しながら誤算といえるのかもしれません。 おわりに 徳川家康・石田三成・毛利輝元三人のそれぞれの誤算とそこからの対応を書状で読んでみると,家康はやはり優れたところがありました。三成は彼なりに動いているとおもいますが、家康ほど書状が残らす、三成の努力の跡は確かめられません。 多くの家康書状の中には東北にいた伊達政宗の最上義光宛の書状もあります。書状が届くまでに何日かかったのか、書状の内容が事実であるのかそれを確かめる時間はあったのか、そういう前提の中でその書状を読んでどんな判断をしたのか。考えてみるのは非常に面白いです。 関ヶ原の戦いにいろいろな形でかかわった武将をざっと並べてみると百人は下らない、九州から東北までそれほど大きな戦いだったことが分かります。 そのかかわった人たちの人生の中で書状を見てどんな判断をして、その人達の一人一人の人生の中で考えたらどうなのか。 家康にも彼の人生があって、信長に屈服したとき、秀吉に屈服したときがあり、その後にチャンスが回ってきて、これを生かしたのが関ケ原合戦。真田の最初のピンチは仕えていた武田が滅びたことで、北条に付くか上杉に付くか、それとも徳川に付くか、さらには秀吉にどう対応するか、そういった経験を経た後の関ヶ原合戦いでした。 関ヶ原合戦に参加した武将たちのそれぞれの歴史を考えながらこれらの書状を読んでいく、大変面白い営みです。これからも続けていきます。 ご清聴ありがとうございました。 |
![]()
2025年1月 講演の舞台活花

活花は季節に合わせて舞台を飾っています。
平成24年3月までの「講演舞台活花写真画廊」のブログはこちらからご覧ください。
講演舞台写真画廊展へ
![]()